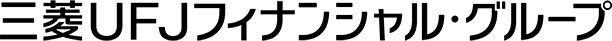作品カテゴリー / 素材|陶磁器 / 陶、色絵、金彩
作品サイズ|幅:38cm / 奥行:40cm / 高さ:42cm
青木 千絵 氏
江戸時代の風俗や信仰を現代の視点でユーモアと遊び心を持って再構成した作品は、思わず笑みがこぼれるような魅力があります。作り手自身が心から制作を楽しんでいる様子が伝わり、見る側にも前向きな力を与えてくれます。その表現の背景には、九谷焼の伝統技法と多彩な加飾が確かな基盤としてあり、自由な発想をしっかりと支えています。今後の展開が楽しみな作品です。
田山 貴紘 氏
社会的なテーマを表現しつつも、モチーフのユニークさに頬が緩んでしまい鑑賞していて楽しい作品。作者の中の変化と社会の変化による作品の変化が今後楽しみ。

作品カテゴリー / 素材|刺繍 / 絹糸、シルクオーガンジー、鉄ワイヤー、
綿布、木、木工パテ、鋼線
作品サイズ|幅:22cm / 奥行:22cm / 高さ:13.5cm
青木 千絵 氏
何よりまず「美しい」と心から感じた点と、非常に完成度の高い作品であることを評価しました。絹の艶やかな美しさを存分に活かしており、自ら染めたという白と藍の静謐な色彩からは、素材への繊細な眼差しを感じました。何百回も針を通す刺繍という丁寧な手作業によって、「日本刺繍」が加飾から解き放たれ、立体的な落ち椿として静かに、しかし確かな存在感を持って立ち上がっている作品だと思います。
秋元 雄史 氏
いい作品である。刺繍という技法を前面化して作品制作上の主要な技法にしている点が興味深く、うまく一つの立体作品にしている。単なる超絶技巧になってしまわないように、糸の美しさ、そのものを優先し、引き出しつつ、椿をデザインしている点も評価できる。繊細さと美しさを兼ね備えた作品である。

作品カテゴリー / 素材|ガラス / ガラス
作品サイズ|幅:36cm / 奥行:18cm / 高さ:65cm
四代田辺竹雲斎 氏
オブジェ作品、インスタレーションと幅広く制作している。技術的な未熟さはあるが、表現が面白く、今後の活躍が期待される。ガラスのインスタレーションなど大規模な展示も期待したい。
中村 弘峰 氏
ガラスという素材の利点と不利点を咀嚼した上で、素材に自分自身を投影して作品表現へと持っていく力をすでに高いレベルで有していると感じました。作品自体は、技術面でもコンセプトや独自性の部分でもまだまだ発展途上であると感じますが、表現活動のスケール感が大きく、これからの展開をぜひ見ていきたいと思いました。

作品カテゴリー / 素材|布 / 綿、黒竹
作品サイズ|幅:41cm / 奥行:35cm / 高さ:35cm
舘鼻 則孝 氏
素材と組織を追求するなかで得られた成果と、それに伴う技法研究から導かれた要素からかたちづくられた優秀な作品。作品を構成する要素には必然性があり、それらを再構築するというプロセスに作家性が表現されている。哲学的とも感じられる作家の思考と素材や技法がリンクする作品展開の今後に期待したい。
中川 周士 氏
作家の使う構造という言葉に共感します。織物の組織構造と社会構造、細胞構造などに相似性を見出し自分の作品に取り入れようとしている姿に面白さを感じました。繰り返されたりする事柄や、集合の中で生まれる自己組織化と創発現象は人類学や生物進化論の中でも注目を集めています。それらは思考より感覚的であり身体的です。人が手で作る工芸との親和性の高い分野であると考えています。作家が素材に触れ「手で考える」ことで導く哲学にも期待します。

作品カテゴリー / 素材|木 / クスノキ、漆、アクリルガッシュ
作品サイズ|幅:55cm / 奥行:10cm / 高さ:37cm
秋元 雄史 氏
残雪期の、まだ雪に覆われた剱岳に伝わる伝説の白鷹を作者が想像力を働かせて造形化した。鷹の両翼の背後には剱岳の山並みが見えて幻想的なイメージ展開である。井波の伝統的な彫刻技法による作品で、さらに、そこに彩色が施されて、新たな井波彫刻の可能性を感じさせるものになっている。
舘鼻 則孝 氏
霊峰立山の古事をその土地の伝統技法である井波彫刻で表現することは、仏師が仏を彫るように信仰を表すことでもあると感じている。鑿と彫刻刀のみで彫られた刃の痕跡が作家の歩んだ道程を表し、その集積によって作品の姿が表現されていることが本作の持つ魅力に繋がっている。

作品カテゴリー / 素材|金属 / 洋白、ステンレス、純銀
作品サイズ|幅:35cm / 奥行:35cm / 高さ:15cm
中田 真裕 氏
洋白、ステンレスという強度の強い金属でできているが中空構造により作品の一部がゆらゆらと揺れる。周りを通るたびに吹き抜ける風を感じる。作者が幼少期から身近にあった豊かな自然を迷いなく表しているところが魅力。将来見る人にも、現在見る私たちにも本物の自然の生命力が感じられ、作った人のことを思わずにはいられない作品の力がある。
秋元 雄史 氏
洋白、ステンレス、純銀などの金属を加工して制作された繊細な作品で、まとまりがある。技術的にも安定していて、見応えがある。「生命の輝き」を蝶に託して表現しているが、象徴的な扱いが作品に深みを与えている。蝶の群像といった様子で、群れている蝶をある動きとして塊感も大切にしつつ表現しており、作品の完成度が高い。

作品カテゴリー / 素材|羊腸 / 羊腸
作品サイズ|幅:35cm / 奥行:28cm / 高さ:42cm
<サポーター推薦コメント>
佐々木 類 氏
以前よりとても興味深い作品だと関⼼を寄せていました。⾃⾝のアイデンティティと素材と制作過程がコンセプトとしてよく考えられている詩的で強くて美しい表現の作品です。また、インスタレーションからオブジェまで⾊々な形態での作品表現にチャレンジしていることも、今後どんな作品が⽣まれてくるのか⼤きな可能性があり、楽しみです。様々な分野で活躍できると思うので、このままどんどん突き進んでいってください。
舘鼻 則孝 氏
本作は、素材や技法に関する習熟された研究と共に、作品を構成する要素の随所に作家自身のアイデンティティを感じることができる秀逸な作品。作家の生い立ちや、文化的背景を作品に投影することは容易ではないが、本作ではそのような要素が紡がれ作品化されている。羊腸という素材から発想された「生命と物質」という主題に基づき「身体」や「器」という視点で再構築されたことで可視化された作品のビジュアルはとても興味深い。

作品カテゴリー / 素材|漆 / 漆、木、麻布、顔料、銀、金
作品サイズ|幅:22cm / 奥行:1cm / 高さ:27cm
上出 惠悟 氏
少し遠くにあって、淡くて頼りないイメージを、時間をかけて額に収める。その手法としての技法に強く惹かれた。
桑田 卓郎 氏
漆の特性を用いて作家自身の表現としてバランス良く表現できている。工芸の現代性を強く感じた。自身が触れたことのない、沢山の技法や手法に触れるのも良いと思う。

作品カテゴリー / 素材|金属 / ブロンズ、真鍮、ガラス、金箔
作品サイズ|幅:3cm / 奥行:2cm / 高さ:4cm
田山 貴紘 氏
大地から植物が生えているような、無機物と有機物、一様と多様、装飾と非装飾を一目見て感じさせられる作品。金属というものの社会の歴史的なものを含めた役割や素材の制約と、世界や自己を対比的に見ているようで、作者のどこか怒りや意志を感じつつ、優しさも感じる。
中田 真裕 氏
鋳造という一つの技法にこだわったことにより、多角的美しさを獲得した作品。工芸は舐め回すように観る人が多い気がするので、ぜひそのように物質の存在感を味わってほしい。

作品カテゴリー / 素材|布 / ウール
作品サイズ|幅:55cm / 奥行:2cm / 高さ:55cm
須藤 玲子 氏
「経糸は空間、緯糸は時間」と言ったのは、染織作家の志村ふくみ氏。作者は慎重に選出した色糸を、計画的にしかも複雑に配列して“空間”をつくり、緯糸には自由で感覚的に色糸を配し時間を織り込んでいるかのようだ。さらに経糸と緯糸を司る織物構造の綿密な計画により、作品全体が制御されているにもかかわらず、どこか穏やかで曖昧さを醸し出している。その理由は、機の上で即興的に行っているフェルト技法の所以だろう。百以上はゆうにある豊かな色彩と、羊毛素材の特徴を効果的に使った魅力的な作品である。
四代田辺竹雲斎 氏
「日常生活の中の感情表現」がテーマという作品だが、見る者を楽しい気持ちにさせ、作者の日々のポジティブ思考を感じることが出来る。技術も高く、色使いが鮮やかである。思わずくすっとさせるタイトルやコンセプト表現が魅力な作品である。

作品カテゴリー / 素材|ガラス / ガラス
作品サイズ|幅:36cm / 奥行:34cm / 高さ:40cm
上出 惠悟 氏
炎に溶け、薄く膨らんだガラスの膜が地面に触れるまでの時の流れを思う。その美しさに強い意志を感じた。
細尾 真孝 氏
作品そのものが放つエネルギーと直感的に「美しい」と感じさせる力を持った、素晴らしい作品でした。

作品カテゴリー / 素材|漆 / 漆、麻布、砥粉、地粉
作品サイズ|幅:57cm / 奥行:25cm / 高さ:30cm
桑田 卓郎 氏
作家のプレゼンテーションを聞くなかで、制作プロセスとともに素材に向き合う姿勢を評価した。漆として古く残っているものや、その関係性、地域性などのプロセスも含め多く漆を知って制作を続けて頂きたいと思う。
細尾 真孝 氏
漆のテクスチャーに洗練されたセンスを感じました。素材としての漆の新たな可能性を感じさせる表現が印象的でした。

作品カテゴリー / 素材|ガラス / 硼珪酸ガラス、Aスキガラス
作品サイズ|幅:30cm / 奥行:30cm / 高さ:35cm
中川 周士 氏
ガラスの異なる二つの技法を組み合わせることで新たな表現に挑戦しようとする姿に感銘を受けました。素材と真摯に向き合い新たな技法を探求する、そこに工芸が工芸であるゆえんを感じます。居場所としてのフレームから外に飛び出そうとする気持ちと中にとどまろうとする気持ちは作家の内面の投影かもしれません。束縛があるから人は自由になれる。今後、造形的魅力を探求し、さらなる飛躍を期待します。
牟田 陽日 氏
技法により生まれる抑制と解放のリズミカルな形状が見ていて楽しい。生物や人体を思わせるようなオーガニックさもあるが、透明なガラスを用いているためプラスチックのような人工的な印象もある。大きさや形状、色彩、他素材との組み合わせなど今後の展開も見てみたい。

作品カテゴリー / 素材|ガラス / ホウケイ酸ガラス
作品サイズ|幅:16cm / 奥行:3cm / 高さ:28cm
中川 周士 氏
あたかも森の落ち葉についた霜を取り出したかのような繊細で優美な表現力は圧巻である。ガラスという素材により溶けてゆく瞬間を固定したかの作品は観るものを引き付ける魅力を感じた。朝霜の薄い氷の被膜が穏やかな朝日の 僅かな温かさで溶ける様をガスバーナーの1000度以上の高温で溶けるガラスで表現している。そのギャップが面白い。ガラスと日々向き合い身近な素材となっている工芸家ならではの感覚であろう。
中村 弘峰 氏
作品から放たれる品位が個人的にはファイナリストの作品中でもっとも強かったと思えました。水や植物をそのままガラスという素材へ変換したという感じが伝わってきて、止まった時間の中に自分が入ってしまったような不思議な感覚になる作品。個人的には今後、ジュエリー的な方向性もいいが、アートとしての作品展開をもっとみてみたいと思いました。

作品カテゴリー / 素材|金属 / 銀、銅、七宝
作品サイズ|幅:5.3cm / 奥行:5.3cm / 高さ:5.3cm
中村 弘峰 氏
作品制作を自分自身が楽しみながら、また鑑賞者を楽しませたいと思っていることが伝わってくるいい作品だなと思いました。技術的にみても金工と七宝をいい塩梅で掛け合わせていて新鮮に感じました。強いて言えば、どんぶりが薄くて金属的でうどんには似合っていないと思ったがあえてのハズしなのかもしれない。今後はもっと広い視野で面白い作品をどんどん作っていってほしいです。
秋元 雄史 氏
伝統的な金工技法を使用して、素材の特性を活かしつつ、化学変化だけで多彩な色表現を盛り込んで、奇妙なリアルさとユーモラスさをもったきつねうどんを制作した可愛い作品。似たような雰囲気で思い起こすのは食品サンプルであるが、それよりもだいぶ小さく、全てがミニチュアサイズでできていて、愛嬌がある。

作品カテゴリー / 素材|金属 / 七宝、銅、銀
作品サイズ|幅:13cm / 奥行:13cm / 高さ:10cm
中田 真裕 氏
七宝作品は銀線の組み合わせによる模様の独創性が好きだ。本作は、それに加えて焼き艶という新しい味わいを みせてくれた。技法ゆえサイズや形の制限がある分、作者の思いの密度が高くなると感じるが、さらにトカゲ愛も強い作者自身の写しのようにも見え、人生に寄り添い励まし続けてくれる存在でもあると思わせることが作品の個性となっている。
牟田 陽日 氏
七宝という極めて難易度が高く時間を要する工芸に、自分の蜥蜴嗜好を取り込みながら、立体的な素地に七宝を施し新鮮な挑戦をしている。ガラスゆえの彩度の高い華やかな印象が多い七宝だが、本作品は色を白系に絞った中で複雑な色彩を見せている。さらにとことん拘りきった七宝蜥蜴も見てみたい。

作品カテゴリー / 素材|ガラス / ガラス
作品サイズ|幅:36cm / 奥行:36cm / 高さ:18cm
佐々木 類 氏
⼀⾒、半球状のシンプルな作品ですが、とても繊細で丁寧な制作過程に好感が持てます。⽇々の⾃⾝の精神や⾝体状況によって変わる様々な線が⽇記のようで興味深いです。また、伝統的な装飾技法のエングレービングは図案を基に具象的な表現が多い中、素地の形に沿ってフリーハンドで抽象的な表現をしていることも技法の再解釈としてこれからの作品に期待しています。
田山 貴紘 氏
シンプルな半球型は、際と円環を表すだけでなく、粒子と波の両面性をもちあわせ、対象物との相互作用によって変化する光がそこを通過することで模様が浮かび上がる事象が、どこか世界や生命を示唆するようで面白い。既存の線を追って次に描かれた線が、実は潜在意識を投影しており、もしかすると、生命の進化の過程も含んだ潜在意識を投影しているよう。ガラスの縁を薄くしていることも、繊細さと境界を鮮明にしており良い仕事。

作品カテゴリー / 素材|布 / 雪、反応性染料、レーヨン、グリッター、樹脂、木製パネル
作品サイズ|幅:40cm / 奥行:5cm / 高さ:60cm
四代田辺竹雲斎 氏
華やかな色使いと作者のキャラクターは、工芸の新しい可能性を感じさせる。賛否があると予想される樹脂を使用するといった思い切った技法は、模索しながら新しい表現を見出したいという思いが見受けられる。常識を打ち破る作品を期待したい。
秋元 雄史 氏
制作過程で生まれる端布を再利用して制作した作品で、あえて色むらがあるように染めた布の上に編み込んだ端布を被せていく。二層の構造が作品の世界を豊かにして見せている。暖色系の色味が美しく、独特のテクスチャーを作り出していて、抽象絵画のような作品に仕上がっている。

作品カテゴリー / 素材|ガラス / ガラス、アルミ箔
作品サイズ|幅:47cm / 奥行:48cm / 高さ:22cm
細尾 真孝 氏
ガラスとアルミ箔が織りなすテクスチャーが、まるで織物を想起させるようで、美しさが際立っていました。今後の展開にも大いに期待しています。
秋元 雄史 氏
今回ガラスの出品が多かったが、その中でも技法的にこだわりを持った作品の一つだったと記憶する。ガラスとアルミ箔の組み合わせによる、異なる収縮率を利用した制作方法を取り入れて、繊細で美しい造形世界を展開する。大きくうねるような全体の動きと繊維を思わせるガラスが縦横に張られた繊細な部分が共存していて、織物のような美しさを感じさせる。

作品カテゴリー / 素材|ガラス / ガラス
作品サイズ|幅:25cm / 奥行:19cm / 高さ:4cm
桑田 卓郎 氏
作家のプレゼンテーションを聞くなかで、作家の制作環境が作品に大きく関係していると感じ、作品を生み出していくプロセスが作品の様にも思えた。
牟田 陽日 氏
作家自身の思考や感情の含まれたプロセスがとても重要な作品。作品自体は最終目的というよりその過程に生まれた一つの固体というような印象を受けた。自分の思考プロセス、あるいは世界観を丁寧にガラスの技法に落とし込んでいる。工芸的にも新しい考え方、素材への取り組み方である。選択する要素についての考えをより深めた上で次のかたちも見たい。

作品カテゴリー / 素材|ガラス / ガラス
作品サイズ|幅:30cm / 奥行:35cm / 高さ:40cm
上出 惠悟 氏
「自らの手でガラスを動かしたい」という、技術に勝るその衝動を応援したい。人間の苦悩や狂気こそが芸術へと“変質”する素材なのだと思う。
佐々木 類 氏
ガラスの素材と素直で積極的に向き合って制作している清々しい作品です。組み作品や光の当て方が違う作品も見てみたいと鑑賞者に創造力を与える作品だとも思います。モールドレスのキルンワークは、ここ数年間で劇的に発展していっているので、自身の表現をさらに探究していくことを大いに期待しています。

作品カテゴリー / 素材|陶磁器 / 磁器、顔料
作品サイズ|幅:33cm / 奥行:5cm / 高さ:33cm
須藤 玲子 氏
作者は焼き物の技術、素材、プロセスを通して自分自身の内面を表しているようだ。泥漿(でいしょう)を素材に、幾度も塗り重ね、焼成し、そのプロセスを繰り返し行うことで得られる饒舌なマチエール。最終的な形態は器のようだが、繰り返し行う作業の結果として、唯一無二の作品が出来上がるという、本質的で力強い造形美がある。土を自分のイメージに転化させ、表面上の、見た目の形を作るのではなく、土そのものに自分を投影しているかのようであり、かつ太古から突如出現したような驚きと力動感を持つ作品だ。
秋元 雄史 氏
陶磁技法を使った絵画のような作品であり、モノトーンが形の微妙な差異を引き立てている。作者本人も「地層」と いう言葉を使用しているように、形の歪みやひび割れによって複雑な面の積層感やその造形的な効果を生み出している。見ていると、どこか世界地図や俯瞰した情景を想像させるところがおもしろい。丁寧な仕事ぶりだ。