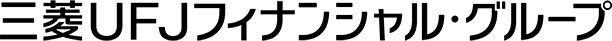変化の時代に経営できる喜びと覚悟
トランプ関税が吹き荒れる重苦しい空気の中、私はこのCEOメッセージの原稿を書いています。
今年1月、ダボス会議に出席しました。テーマは2つでした。「アメリカ」と「AI」です。「アメリカ」については、トランプ政権が始まり規制緩和が進むことで経済が大きく拡大する、さまざまなポジティブな動きが出てくる、この流れに遅れてはいけない。そのような熱気を感じました。実際にアメリカの参加者からは高揚感が伝わってきました。そして、もう一つの話題は、やはり「AI」でした。全ての議論がAIの話につながり、もはやAIなしではどのトピックスも語れなくなっていました。AIを通じて、今後のビジネスは大きく変わるのだと改めて認識しました。
4月に入り、関税の議論が始まりました。戦後80年の世界経済秩序への挑戦とも言われています。トランプ政権とAI、この2大テーマはどちらもいわば既存秩序のDisrupterでもあると理解しています。この文章が出る頃に世界がどのような状況になっているかは、正直、よく分かりません。4月末、モルガン・スタンレーの取締役会に出席するためにニューヨークへ、5月初めにはバーゼルの会合に参加するためにヨーロッパを訪れ、その機会に色々な方とお会いしました。ダボス会議の時とは空気が一変していました。不透明感が全体を覆い、リスクオフムードとなり、資金と資本はその行き先を探しているようでした。アメリカ人の中には不安を抱いている人たちもいました。一方で、不安を抱えつつも、次に来るチャンスに向けて準備を怠ってはいけない、という顔もしていました。
今年は難しくも面白い年、歴史的に振り返ると大きな転機となった年になるのだろうと直感しました。大切なことは、自分のパーパス、軸を確りと持ち、自分の頭でよく思考すること。歴史的な変化の年で苦しい局面もあるかもしれませんが、このような時代に経営ができることを喜びたいし、そうでなくては生き残れない、そう覚悟しています。ただ、よく考えればいつの時代も環境は難しく、経営は簡単ではありません。MUFGも発足してからの20年間、その時々の環境に合わせ、時代を読み解き、必死で対応してきました。だからこそ、今があるのだと思います。
まずは「アメリカ」と「AI」に関する足元の環境・課題認識から始め、これからの不透明な時代にどのように経営に取り組んでいくかをお伝えしたいと思います。
環境・課題認識
トランプ政権の政策転換は、ある意味、保護主義の台頭ではありますが、経済危機が発生していない中での初めてのケースではないかと思います。これは、現行の国際システムの歪みのもとで蓄積した米国の不満の顕れであると考えています。現行の国際通貨体制では自律的に是正できない構造的な課題であり、世界経済秩序の変革なしでは解決できない可能性があるということをよく理解しておく必要があります。このような状況において、日本は今後の成長に向けて構想を練り直す必要があると思います。そしてMUFGには、日本を代表する金融グループとして、日本経済の力強い成長を作り出すことに貢献する責務があると考えています。MUFGは、この20年を通じて、どのグローバルバンクとも異なるユニークな事業ポートフォリオやネットワークを築いてきました。それらを活かして、日本や世界のためにできることはまだまだたくさんあります。
次に、AIです。2023年、GPT-4の登場で世界は衝撃を受けました。2年前のこのメッセージでは「AIは内容を理解していないのではないか」と述べました。昨年は「少し理解が近づいたかもしれない」と書きました。その後、生成AIはOpenAI o1モデルの登場で大きく進化しました。そしてそれはさらに進化しています。数学的アプローチ、量子などの物理的アプローチ、脳科学等の生物学的アプローチとさまざまな研究が各国・各分野で進んでいます。計り知れない飛躍の可能性もあります。AIによる思考の一部をアウトソースする動きが、「思考のDX」に始まり、実はさらに深いところまで既に入り込んだ可能性もあります。そして今、私が最も関心があるのは「理解するとは何か」ということです。
そもそも人は言語を使って何をしているのでしょうか。私は、言葉はコミュニケーションのツールだと思っていました。しかし、アメリカに赴任して英語のコミュニケーションに苦労していた時に、ふと気がつきました。言語は考えるツールなのだと。日本語の場合は無意識のうちに、話しながら考えて、考えながらまた話すというサイクルを繰り返していたのです。ところが英語の場合は日本語のように考えられないので、自分の話したいように話せず、会話を通じて話したいことを深めることができませんでした。話をしながら、自分でも知らなかったことに気がついたり、論点がクリアになって頭が整理されたりという経験は皆さんにもあるでしょう。まさに、言語を使うことで人は思考し、物事を理解するのです。
これまでのデジタルやIT技術は、人間の外側で私たちの活動をサポートするツールでしたが、生成AIは人間の内側に入り込み、私たちの思考を代替し、拡張させる可能性を秘めています。このポテンシャルをいかに理解し取り込めるかは金融だけでなく、おそらく全ての産業の経営における大きなテーマだと思っています。Salesforce社のMarc Benio CEOは、「人間だけで経営を行うのは、今が最後の世代である」と言っています。これからの経営者には、AIを前提とした組織運営を行うことと、今その準備が求められています。(コラム1)
MUFG20年の振り返り
第一フェーズはMUFGの誕生と基盤構築の時代です。モルガン・スタンレーとの業務提携や投資銀行の強化を進め、国内では三菱UFJニコスの誕生やアコムの子会社化を実現しました。この時期に築かれた「グループ基盤」が、今日のMUFGの礎となっています。
そして、第二フェーズでは、ASEANでのプレゼンスを強化しました。タイのアユタヤ銀行(KS)、インドネシアのダナモン銀行(BDI)など、アジアの商業銀行への出資を積極的に行いながらASEAN地域でのフットプリントを拡大しました。第一フェーズと合わせて、MUFGのユニークな事業ポートフォリオの土台ができました。
最後に、足元のビジネスモデル変革に挑戦した第三フェーズ。国内では「ビジネスの強靭化」、海外では「再構築(量から質への転換)」を進めました。手数料収益などの「稼ぐ力」を強化し親会社株主純利益が増加するとともに、採算を重視した運営にも取り組み、リスクリターンも大幅に改善しました。また、国内の店舗統廃合を通じた経費削減により筋肉質な財務構造への変容を実現しました。さらに、新たな領域としてAM/IS分野の買収や国内外のデジタル分野への出資、ファンド設立を積極的に行う一方、米国ユニオンバンク売却を実行し、スピードを意識したインベストメント・ダイベストメントでポートフォリオを見直しました。「ROE経営」を掲げて事業ポートフォリオの最適化に取り組むとともに、「世界が進むチカラになる。」というMUFGのパーパスを据え、これを経営の意思決定の拠り所としました。時代に即した機能を提供するべく変革を続け、さまざまな取り組みが結実したことで、24年度の収益額はコロナ禍以前の2倍に拡大し、ROEも9.9%まで大きく改善。質・量ともに大幅な成長を遂げ、中長期的なROE目標9-10%に到達しました。
今後のめざす姿
こうした20年の歴史を踏まえて、MUFGはこの先どこへ向かうのか。
私たちは、今年5月に、中長期のROE目標(東証定義)を12%程度まで引き上げることを発表しました。時価総額では30兆円をめざしたいと考えています。そのためには、これまで築いてきた事業ポートフォリオに磨きをかけ、より一層強くしていく必要があります。
まず、日本経済がこれから成長軌道を描く中で、日本最大の金融機関として産業政策やエネルギー政策等を牽引し、お客さまとともに日本の成長を創出していきます。またリテールビジネスでは、5月に発表した新サービスブランド「エムット」を軸に据え、圧倒的な顧客基盤をさらに確たるものにすべく、外部のパートナー企業と協業しながら、強靭なプラットフォームを構築していきます。また、AM/ISやアジア、デジタル、そして米国やインドのような成長する国々へのインオーガニック投資にも積極的に挑戦し、私たちのユニークな事業ポートフォリオをより洗練させていきます。大切なのは、社会課題解決があってこそ私たちのビジネスや成長があるということです。7つの事業本部は、グループの総合力を活かしてグローバルベースで社会的価値と経済的価値の両方を追求し、MUFGの企業価値を高めていきます。
同時に事業戦略を支える企業変革にも挑戦し続けます。CEO就任以降、カルチャー改革に取り組んでいますが、社員が自然に「主体的に考え、決断し、行動する」ことができる強い組織をめざします。その上で、これから重要になるのはAIです。AIの話題ではどうしてもアプリケーションやユースケースの議論に目が向きがちですが、大事なのは、データ、そしてプロセスやルールといった「基盤」を作れるかどうかです。データの整備や価値化に取り組み、AIと人とが自然に意思疎通、意思決定ができる組織環境の構築をめざします。AIエージェントの時代に、データを知識に、知識を力に変える。その先に広がる未来を想像するだけで心が躍ります。力強い成長を実現しながら、金融機関の枠を超えて社会に革新をもたらす存在へと変貌を遂げ、「世界に選ばれる、信頼のグローバル金融グループ」になる。これが、私たちがめざす姿です。
一方で、昨年は、これまで築いてきた信頼・信用を揺るがす、業界にも影響を与える不祥事案が発生しました。経営として極めて重く受け止めています。リスク認識や内部管理体制、行内ルール等を不断に見直し、再発防止策を徹底していきます。社会やお客さまからの信頼・信用がなければ、私たちはいかなるサービスも提供できません。社会が変化しようとも、法規制や社会規範、倫理に沿った行動を取ることが最優先であり、変えるべきもの、変わってはならないものを確りと見極めていきます。
未来につなぐ
ここから、中期経営計画(中計)の具体的な進捗についてお伝えします。まずは「社会課題の解決~未来につなぐ」です。儒教の教えに「先義後利(せんぎこうり)」という言葉があります。これは、人としての道義が先にあり利益はその後についてくるという、義と利の順序を明確にしています。まず、社会やお客さまの課題があり、その解決に貢献するためにビジネスがあるという順番で考えることが重要です。目の前の業務に向き合っていると、どうしてもビジネスが先に来てしまいがちですが、考える順番を変えなければならないと社内でも伝えてきました。社会課題の解決に金融サービスを通じて貢献する。その結果として、お客さまやMUFGの経済的価値が向上する。お客さまとMUFGの社会的価値と経済的価値をつなぎ、両者を相乗的に高めていくことが、MUFGの責務であり、果たすべき役割です。10年後のMUFGは「いかに社会課題の解決に貢献できるか」によって決まると考えています。
社会課題解決に対する本気度を感じていただきたいと思い、4月にはレポート「未来につなぐ~MUFGの社会課題解決~」を公表しました。社員起点での取り組み実績に加え、私たちが社会に対して創出したいインパクト、めざす姿を整理しています。しかし、社会課題の解決に向けた取り組みはまだまだ道半ばです。例えば、MUFGの取り組みが社会にどのような影響をもたらしているかを表した「インパクト指標」の設定にあたっては、一歩踏み込んで定量的な目標の設定にチャレンジしましたが、「社会へのインパクト」を全ての課題において定量化しきれているわけではありません。ステークホルダーの皆さまとの対話を深めながら、私たち自身の取り組みを進化させていきます。
成長をつかむ
国内リテール顧客基盤の強化
まずは、国内リテールビジネスです。私たちが持つお客さまの基盤は最大の強みの一つです。お客さまが次の世代に資産を継承していく中、この基盤を維持・拡大させるためには、私たちも次世代との取引をさらに強化する必要があります。三菱UFJ eスマート証券やウェルスナビの完全子会社化、三菱UFJニコスのシステム統合の進捗など、攻めに転じる態勢が整いました。若年層にとっても利用しやすく、また全ての世代のお客さまに身近で便利な金融機関であることをめざします。
今年5月には「つながる」をキーワードに、「エムット」を発表しました。国内No.1金融グループとして、あらゆる人の、日常とライフステージにやさしく寄り添える金融サービスを提供したい、そのような思いから誕生した「ライフステージ総合金融サービス」です。まずは、「三菱UFJ銀行アプリ」を中核にさまざまな金融サービスをシームレスにつなげました。また、日々の生活でMUFGのサービスをご利用いただくため、簡単にポイントを貯めることができる新しいポイントアッププログラムを作り、そのポイントを世界のVisa加盟店でご利用いただけるようにするなど、利便性と利得性を強化していきます。26年度中にはさまざまな展開を予定しています。まず、MUFGグループと「つながり」、より「長く」使っていただくほどお得になるロイヤリティプログラムやグループ共通の「エムットポイント」を開始します。また、デジタルとリアルの「いいとこ取り」をした全く新しいコンセプトのデジタルバンクを立ち上げます。加えて、相続などの重要なライフイベントでも選んでいただくべく、新たなデジタル相続プラットフォームの検討も進め、大切な資産を次世代へ残すサポートを行います。MUFGは、銀行、信託、証券、決済、資産運用など、個人が一生涯で必要とする金融機能の全てを有する唯一の金融グループです。それぞれの機能をつなげることで、お金を「つかう」「ためる」「ふやす」、そして次世代に「つなぐ」、といったお客さま一人ひとりのニーズに柔軟にお応えし、一生に寄り添うサービスを展開していきます。
重視しているのは「お客さま第一主義を貫く」ということです。お客さまの利便性を第一に、コアの金融サービスはグループ内で完結させつつ、プラットフォームは外部のパートナー企業と組んで強化していく方針です。今後は「エムット」を軸にお客さまとの“つながり”を深め、グループ間の“つながり”を加速させ、圧倒的なプラットフォーマーとして、もっと“つながる”MUFGをめざします。
アジアプラットフォームの強靭化
収益の2割を占めるアジアにおいて、MUFGがAPAC域内で保有するエクスポージャーは世界最大です。これまでのアジアビジネスを振り返ると、KSやBDIはオートローン等のリテールビジネスを軸に業績を伸ばし、アジアの営業純益はこの10年で5倍に拡大、2024年度は約5,000億円と過去最高益を記録しています。足元では、家計債務の高止まりや高齢化社会、利下げなどマクロ環境の変化が起きていますが、中長期的な目線で見れば引き続きポテンシャルは高く、アジアがMUFGの第二のマザーマーケットである点は不変です。引き続き、パートナーバンクの事業競争力を高めながら、デジタル出資先の拡大、財閥親会社との協働、インドの成長機会の取り込みなど、「MUFG経済圏の構築」に取り組みます。次期中計最終年度の2029年度には、当期純利益(償却前)を24年度対比で1.6倍程度まで引き上げる計画です。アジア全体の収益規模を拡大しながらアジア×デジタル戦略を進め、GCB事業本部の営業純益の約2割が「デジタル」が占めるという、より一層バランスの取れた安定的な事業ポートフォリオを実現します。
また、こうしたアジアビジネスの展開は同時に、「金融包摂への貢献」という点で社会課題の解決にもつながります。各国で暮らすさまざまな人に対して金融サービスへのアクセス拡大を実現し、経済的な機会を提供することで、貧困削減や生活の質の向上を促進します。
GCIB・市場一体モデルの進化とモルガン・スタンレーとの協働
GCIB事業本部と市場事業本部の一体運営を通じて、ビジネスモデルの進化に取り組んできました。O&Dやクロスセルなどの手数料収益拡大に向けた取り組みが着実に実を結び、バランスシートの収益性は大幅に改善しました。今後は、証券化ビジネス強化などを通じて、リスク分散とリスクテイクを一段とレベルアップしていきます。
とりわけ、世界最大の経済圏である米国でのビジネスは、MUFGの収益の3割を占めています。2022年のユニオンバンク売却後は、ホールセール事業に経営資源を集中させました。このホールセール事業は、ユニオンバンク売却によって減少した収益を大きく上回る実績を出しており、その後も利益成長を続けています。また、MUFGの強みであるプロジェクトファイナンスの組成額は、15年連続で米国1 位、3年連続で世界1位を獲得するなど、競合他社を上回るパフォーマンスを上げています。
モルガン・スタンレーとの協働も着実に進化しています。今年5月には、MUFGとモルガン・スタンレーで共催した「Japan Summit」でTed Pick CEOとともに登壇する機会があり、約2,000人の方に提携の成果や今後の展望をお伝えすることができました。Tedとはかれこれ20年来の付き合いです。ダボス会議では、期間中に行われたモルガン・スタンレー主催のスモールディナーに招待されました。そして、名立たる投資家やCEOの前で私を紹介するとともに、2008年の出資当時のエピソードやMUFGに対する謝意を語ってくれたのです。心のこもった挨拶で、思わず胸が熱くなりました。また、Tedと私の関係だけではなく、両社で協働する人の裾野や協働のテーマが広がっていることも提携の発展を物語っています。さまざまなレイヤーで交流が進み、唯一無二の信頼関係を構築できていると実感しています。これからもお互いの強い信頼関係のもとに協働を進化させていきます。
会社がかわる
カルチャー改革
CEO就任以降、変化の時代に生き残る組織となるために、エンゲージメント経営を実践し「挑戦とスピード」のカルチャー改革に取り組み続けています。カルチャー改革の重要性は社会の変化とともにますます大きくなっています。「MUFGは変わった」と思われるためには、社員一人ひとりのマインドセットの変革が鍵です。パーパスの実現に向けて挑戦する風土を醸成し、社員のエンゲージメントを高めることが重要です。そのためには、過去を振り返るのではなく「未来にどうなりたいか」を起点に物事を考えていかなくてはなりません。現在の延長線上に未来はなく、現在に固執する限り未来を語ることはできない、と社内でも繰り返し伝えています。今中計で重視しているのは、「スピード」です。環境変化へ迅速に適応する組織作りのため、組織間の連携を高める機能横断のチーム「アジャイル変革推進室」を設立し、アジャイル運営の導入に着手しています。今後はこの運営を適用する領域を拡大し、企業変革につなげていきます。
また、国内外のデジタル企業との協業も、社員の意識が変わるという面でカルチャー改革につながっています。投資先のCEOから「MUFGは日本で最大規模の金融機関なのでスピード感に欠けると思っていたが、驚くほど迅速に意思決定している」と言われ、私たちのカルチャー改革が着実に進んでいることを実感しました。異なる文化を持つ企業との協働は、双方に刺激を与え、進化を促します。
人的資本経営
1,200の挑戦、MUFGの成長
「MUFGを覚醒させたい」
昨年のCEOメッセージでお伝えした私のメッセージです。そこから1年経ちましたが、その思いはさらに強くなっています。
今年4月にMUFG部店長会議を実施しました。持株、銀行、信託、証券、ニコス、アコム、三菱UFJアセットマネジメント、各パートナーバンクから、国内外合わせて総勢約1,200人の部店長が集まりました。この規模でリアルに集まるのは、2005年にMUFGが発足して以来、初めてのことです。とても迫力のある光景でした。
1,200人の部店長にこのメッセージを改めて伝えましたが、懇親会の場などで、一部の部店長から「自分の支店(部)を覚醒させます」と言われました。ハッとしました。各部店長の先には、15万人を超える社員がいる。MUFGが1,200の組織からなる集合体だと考えれば、その一つひとつがそれぞれの強みを最大限に発揮し、真の意味で覚醒すれば、MUFGはもっと強くなれると確信しました。MUFGには、これまでの長い歴史の中で築き上げた信用・信頼、圧倒的なお客さまの基盤、グローバルネットワーク、そしてグループ総合力があります。私がCEOとして果たすべき役割は明確です。カルチャー改革を不断に進め、有形無形の障壁を取り払い、風通しの良い職場で自由闊達な議論が交わされること。社員一人ひとりが変化を恐れず、挑戦し続けられる環境を整えること。そして、それを全力で後押しすることです。変化の波は時として荒々しく、挑戦の道は険しい。しかし、挑む力を持つ者が未来を切り拓くことを、私は何度も目の当たりにしてきました。この覚醒のプロセスを支援することが、私の使命であり責務です。
変化の激しい時代にあっても、「世界が進むチカラになる。」というMUFGのパーパスは不変です。変化の時代だからこそ、パーパスを拠り所として、社員が「主体的に考え、決断し、迅速に行動する」という思考力と行動力を高めていければ、本当の意味で「MUFGの覚醒」に近づいていけると考えています。「先義後利」の精神のもとで、社会的価値とともに経済的価値を両輪として追求することこそMUFGが果たすべき責務であり、信頼・信用を築いていくための軸となります。私もCEOとして、覚醒の先にある未来を切り拓いていくために、MUFGという組織が持つポテンシャルを最大限に引き上げていきます。この覚醒への挑戦は、私たちが変化を恐れず、むしろ変化を力に変えて進化し続ける決意の表れです。
コラム1:AIの本質とはなにか - 代替と拡張、具体と抽象 -
AIの本質とは何か。そのような問題意識を抱く中、社会学者として有名な大澤真幸さんの「生成AI時代の言語論」に出会いました。色々な示唆のある興味深い本で、思わず大澤先生に連絡し、対談をしました。
私は、物事を抽象化・一般化するのは人の方が優れていると考えています。ただ、AIを使うと、さらに深く議論ができ、また、高く抽象化できる。AIの議論をすると「代替される」、「仕事がなくなる」という話がよく出てきます。実際、これまでは機械が人の仕事を代替し、ITが事務作業を行ってきました。今では、思考においてもAIが人のやることを代替することが可能になっています。それにより、例えば、企業分析の一部をAIが効率的に行うことでジュニアアナリストの仕事がなくなると言われています。ただ、AIの本質はそこにはないと思っています。
もう一つ大切な議論があります。大澤さんから学んだ「失敗の引き受け方」という考え方です。AIが出す答えは時に間違っている可能性があります。また、批判的にAIの解を受け止める必要もあります。AIが失敗した時、自分のこととして人間がそれを受け止める覚悟があるかという視点です。AIがプロセスを担い、人間が目的をコントロールするという役割を明確にしなければなりません。課題の設定までもAIに任せてしまえば、AIに乗っ取られてしまうというリスクもあるでしょう。
私たち人間に求められることは、高いレベルの思考力と行動力です。人間には、AIを捨て駒として活用しつつ、ブレークスルーできる可能性があると大澤さんは仰っていました。そのとおりだと思います。思考力を養う上では、いつの時代にも普遍的な価値を持つリベラルアーツが重要となります。また、行動力の結果として積み上がるリアルな経験知を高めていくことも重要です。MUFGとしても、社員一人ひとりが、このような力を着実に高めていき、人とAIを融合させたAI Nativeな組織に生まれ変わることをめざしていきます。
コラム2:もう1つのCEOメッセージ

MUFGでの生成AI活用に向けた座談会
「AIにもCEOメッセージが書けるのではないか?」そんな疑問から、生成AIを活用して「AI版CEOメッセージ」を作成してみました。過去のCEOメッセージや社内外で私が発信した内容に加えて、外部機関による統合報告書の評価基準もAIに学習させました。また、常に統合報告書の評価が高い伊藤忠商事の岡藤さんのCEOメッセージも参考にさせていただきました。AIが書いた最初のドラフトは、文章はきれいなのだけど、どこか無機質で単調。大澤さんが仰っていた、「AIのアウトプットは優秀だが平均的」、まさにそんな印象でした。一方で、「なるほど」「うまいな」と思える表現もあり、AIが作った表現をもとに私自身の考えを深く掘り下げることで、「思考を拡張する」プロセスを実践することもできました。
こちら(PDF / 167KB)もぜひご覧ください。今後もあらゆる領域でAI活用を進めます。